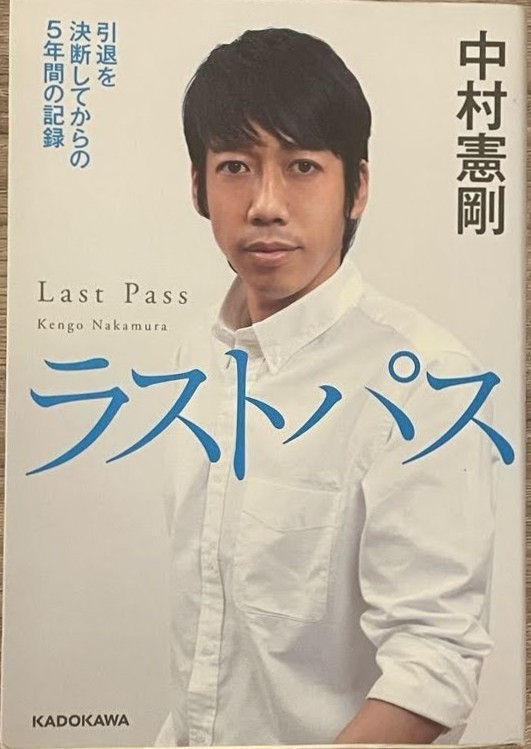「スポーツを読む」第23回 小澤一郎『自主練もドリブル塾もないスペインで「上手い選手」が育つワケ』ぱる出版(2024年)
- 江戸川大学マスコミ学科

- 2025年11月18日
- 読了時間: 2分
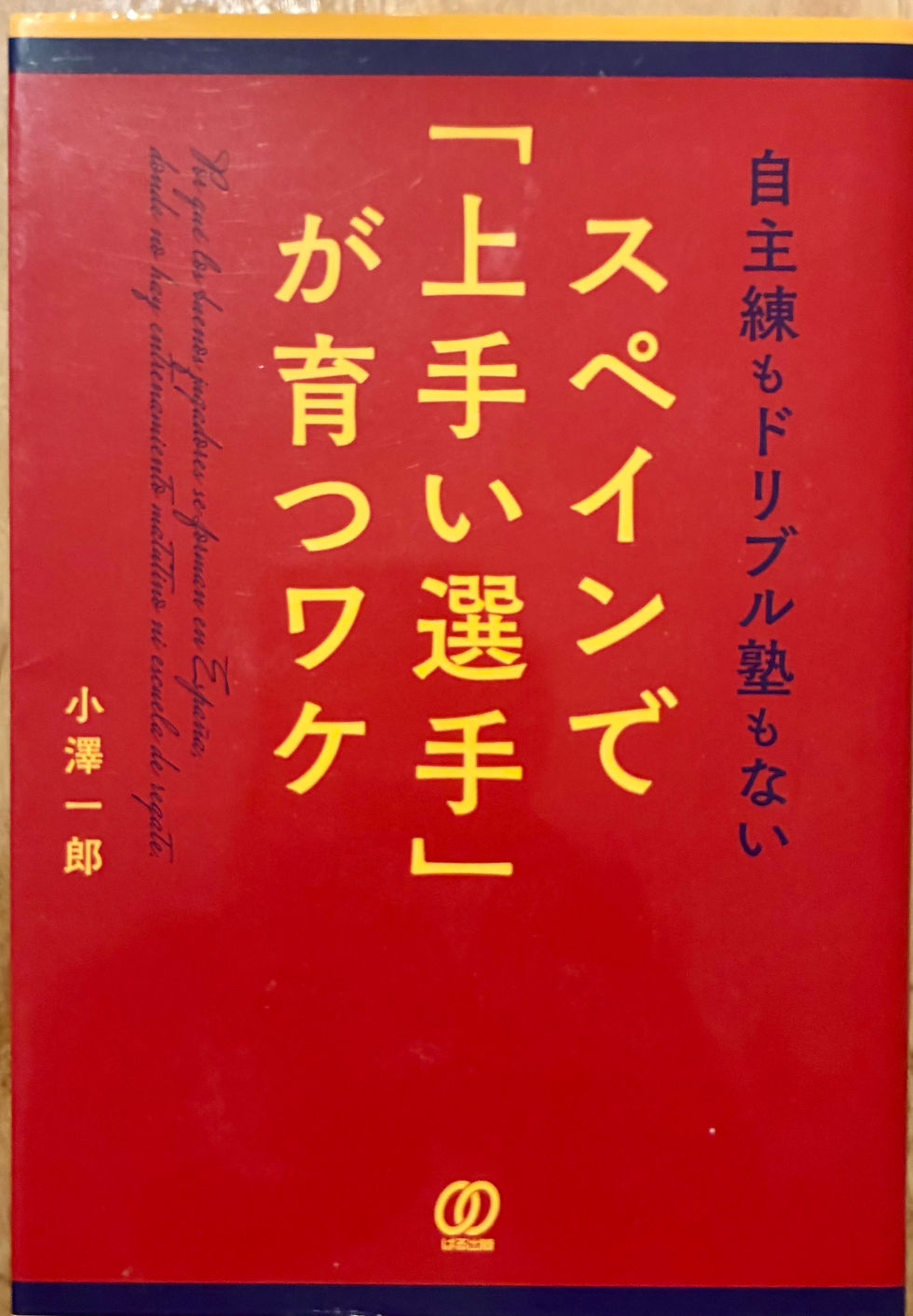
サッカーは最もグローバルなスポーツである。そして、国によって指導方法が全く異なっているという。本書は、常にFIFAランキング上位に座るスペインのサッカー指導における考え方に焦点を当て、日本との違いを説明している。
著者はスペイン在住歴のあるサッカーライターで、育成年代の指導経験もある。スペインと日本の根本的な違いは、競技を始めた時からあると指摘している。
日本のサッカー少年は、リフティングやパスなど基礎的な技術練習から始めることが多い。学校でもクラブでも教わるのは、まず技術である。だがスペインでは、最初から組織的なプレーを教わるのだという。
そしてサッカーを始めた子がすぐに大人と同じサッカーをする。スペインには育成年代からプロまで変わらない「PAD+E」という共通認識が存在する。「PAD+E」というのは「認知」「分析」「決定」+「実行」という意味である。ゲームに必要なこのプロセスが育成年代から頭に叩き込まれていて、ゲーム進行を考えるサッカーが浸透しているのだ。
少年サッカーにおいて「上手いサッカー選手」という概念が両国では相当違うようだ。ドリブルやトラップなどの技ができることを指すか、ポジショニングを理解して動くことを指すかだ。実際に日本の小学低学年のサッカーは団子サッカーになりがちなのだが、スペインではフィールド内に審判とは別にコーチが常に立ち、試合を止めて位置取りを説明することが多いという。
サッカー観戦が趣味の私は普段から各国のリーグの試合を見ている。その中でスペインのリーグは、チームとしての反応や切り替えが速く、サッカーIQが高いと感じることが多かった。日本のJリーグも年々レベルが上がっているが、いまだスペインリーグには及ばない。何が一番違うのだろうかと気になっていたときに、この本を見つけた。サッカーに対する根本的な考え方の違いが分かる本である。
(江戸川大学マスコミ学科、鈴木成真)