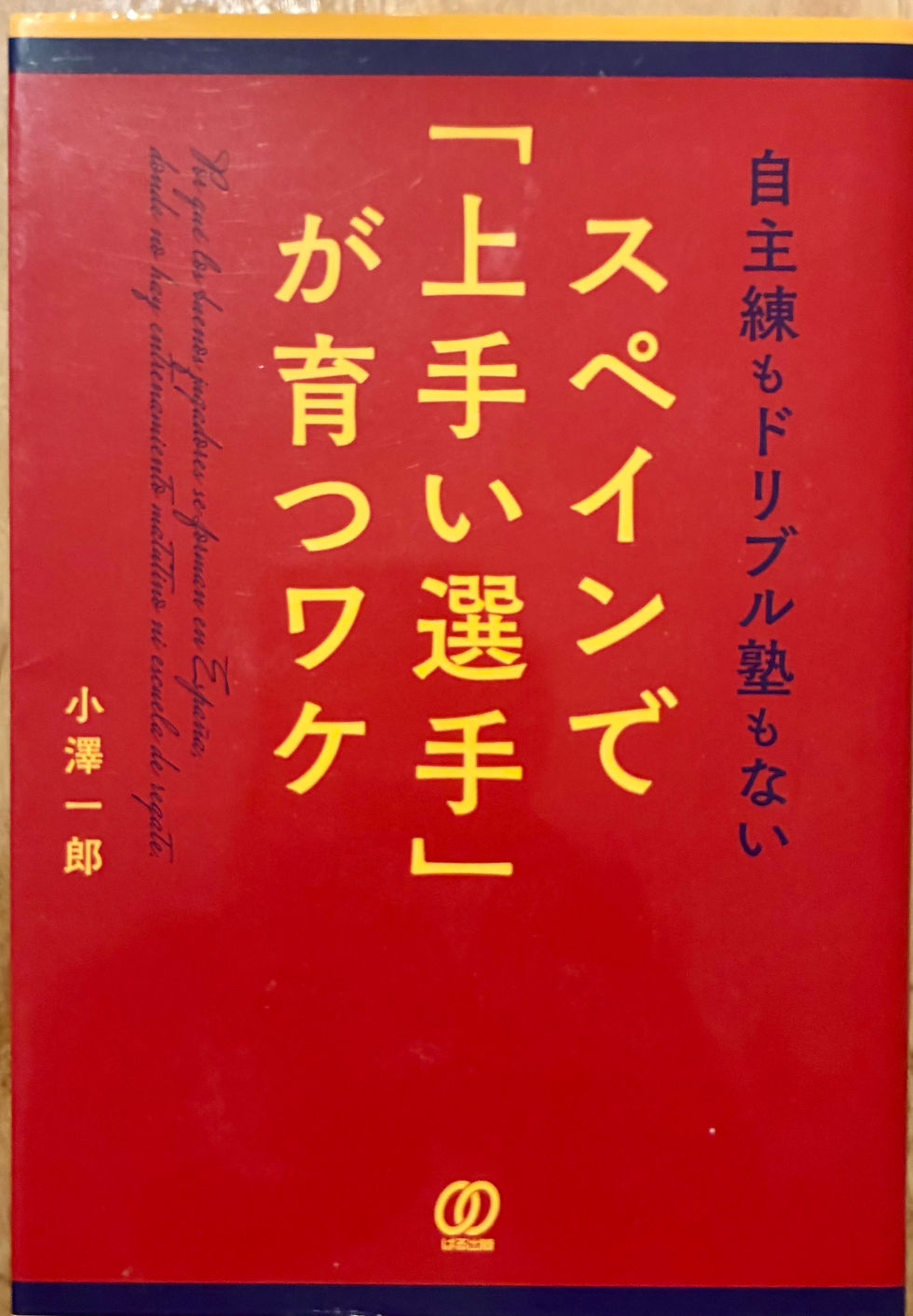【スポーツを読む】第16回川田将雅『頂への挑戦 負け続けた末につかんだ「勝者」の思考法』KADOKAWA(2023年)
- 江戸川大学マスコミ学科

- 2024年10月23日
- 読了時間: 3分
更新日:2025年5月20日

「ジョッキーになるしかない。一番を目指すしかない」と15歳で覚悟を決めて競馬学校に入り、10日目で落馬して右足首を骨折した。それが日本を代表する騎手となった川田将雅の騎手人生のスタートだった。本書は2021年にラヴズオンリーユーに騎乗し、日本人として初めてアメリカ競馬の祭典ブリーダーズカップ・フィリー&メアターフを制した川田の半生記である。
川田は曽祖父が騎手で、祖父、父がともに調教師という一族に生まれたが、家族からは一度も「ジョッキーになれ」と言われたことはなく、競馬学校入りは自分で決めた。だが入学直後の骨折で教官に「やめます」と伝えると、両親は許してくれなかったという。本人も止められることを半ば期待して、やめると言ったのかもしれない。
怪我をしている間に同期の中で圧倒的に馬乗りが上手く、いつも教官に褒められていた津村明秀の乗り方を参考にした。しかし背が高く手足の長さも川田とは違う津村と同じ乗り方をするというのは難しかった。そこで同期の乗り方を「自分流に再現する」ことを覚えた。その結果、怪我が治って迎えた実技試験で津村を抑えて1位を取った。川田はプロとしてデビューする際にも、自分と共通点が多かったミルコ・デムーロを参考にしたと振り返っている。
私は実家が中山競馬場に近く、幼いころから両親に連れられてよく競馬を見に行き、物心つくころには騎手になりたいと思っていた。小学5年から中山競馬場の乗馬センターに通い、高校3年まで馬に乗った。
乗馬において自分のスタイルというのは、崩れない硬いもののイメージではない。馬の特徴を感じ取り、どんな馬にも合わせられる自分をつくりあげるのである。フォームだけをなぞった型ではなく、もっと本質的なものだ。
川田は15歳の時の骨折によって、独りよがりにならずにすんだのだと思う。「自分流に再現する」というのは、形をまねずに、他人を観察してエッセンスを手にすることだろう。
人との出会いや自分の発言に責任を持つことの重要さについても、川田は述べている。騎手という職業は馬主の依頼によって成り立っている。だから常に誤解を与えず、嘘をつかない言葉選びを心掛ける必要がある。馬に乗るということは、それだけで多くの人に支えられているということなのだ。
それはよくわかる。私は試合で結果を残すことはできなかったが、高校2年時に少年団の団長に就任し、40人程をまとめる大変さを学んだ。幼いころ夢見た騎手になることはなかったが、お世話になった乗馬センターで大学入学後にアルバイトをすることでも、発言に責任を持つことや事前の準備を怠らないことを学んだ。乗馬を8年間やり通したことで、馬を知ったのはもちろんだが、それ以上に人間関係を学んだ。
競馬に興味がない方も、いや競馬を知らない方にこそ、手に取ってもらいたい一冊だ。
(江戸川大学マスコミ学科、大谷侑生)